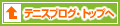注射2006年10月23日
皆さん、いかがお過ごしですか? 根津甚八です。
昨日、遅まきながら、初ものの柿を食べました。
残念ながら、種無しでした。というのは、柿の実で一番好きなところが、種のまわりの、あのツルヌルしてる部分だからです。
あのチョット色っぽい食感が堪らないのです。

柿といえば、俺が生まれた山梨の都留の家の庭には、大きな柿の木がありました。
柿の木の他にも、松、楓等、色んな樹木が植えられていて、今思えば、かなり大規模なものでした。中央にデカイ溶岩が枯山水風に配置されていて、北側の縁に漆喰造りの二階建ての蔵。その右手に瓦屋根の裏門。そこから、隣家との堺の塀に沿って、細長い物置小屋があり、その小屋の端に、立派な柿の木はあった。木登りして遊ぶのに手頃な枝振りで、よく登ったものでした。
ところが、この木に生る実は渋柿で、生では食えない。しかし、実は沢山生るので、母が、軒下に吊るして干し柿にしたものを、おやつで食べたものでした。
軒下に整然と吊るしてある橙々色の干し柿。あの頃は、ごく当たり前の秋の懐かしい光景だったのに、今では滅多に目にする機会もない。
都会の風景は、急速に季節感を感じさせる風物を失っている。
などと、シンミリしてしまうのは、やはり「秋」が深まってきたからでしょうか?
今日は、前回の話に出た映画「さらば愛しき大地」を撮っていた時の、エピソードを紹介します。
あれは、向田邦子さんの「隣りの女」というテレビドラマに出演した、翌年であった。
マネージャーから「柳町光男監督自ら出演依頼があって、シナリオが届いてるから、読んでみて」と言われ、手渡されたのは、なんと!!!監督が自ら書いた生原稿のコピーの束であった。
出演依頼の際、普通は、きちんと製本された台本が届けられるのが当たり前だから、これには、少々驚いた。
その日の夜、ベッドに入ってから、寝る前にザッと目を通すつもりでコピーの束を読み始めた。ところが、一旦読み出したら、話の展開の早さと、濃密さと迫力に圧倒されて、一気に読み切ってしまった。その夜は興奮して中々寝つかれなかったのを覚えている。
読み終えて、「演ってみたい」と思ったと同時に、「演っていいのか」という迷いもあった。それは、俺にオファーされた主人公・幸雄の役どころに原因がある。
幼い息子二人を事故で失ったことを機に、幸雄の人生の歯車は狂い始め、愛人へ、覚せい剤中毒へと堕ちてゆき・・・というキャラクター。いわば破滅的な「汚れ役」である。
当時の俺は、二枚目路線でいっていたから、(ウォー、コッ恥ずかしい!)
この、シャブ中のダンプの運転手・幸雄役は、それ迄の根津甚八のイメージをぶち壊しかねない大きな賭けでもあったのだ。
結構迷った挙げ句、演ることにした。
やはり、シナリオの持っている力強さと、柳町監督のデビュー作「十九歳の地図」に感激していた俺は、監督・柳町光男に対する強い興味が引き金となった。
演ると決めたはいいが、「幸雄」を演じるためには、準備しなければならないことが、大きく四つあった。
一つは茨城弁をマスターすること。映画の舞台は、茨城県鹿島の田園地帯。
「幸雄」は、その一角にある農家の長男という設定である。可能な限りナチュラルである方が望ましい。それに、柳町監督自身が茨城出身であるから、なおさら完璧を目指したいと思った。
状況劇場時代に、韓国、バングラディッシュ、シリアのパレスチナキャンプ地と、それぞれの国の言語で台詞を丸暗記して上演した時、俺の台詞は、80%ぐらい通じていたという実績から、いくら馴染みのない言葉の台詞でも、集中特訓すれば茨城の人が観ても、納得させる自信はあった。
二つ目は、10トン積みダンプカーの運転。
役の職業がダンプの運転手なのだから、当然一般道での運転のシーンがある。街中を荷台を上げっ放しで、電柱をなぎ倒し暴走する場面(このシーンは、予算上等の理由で、撮影されなかった)まであるのだ。大型四輪の免許は、必須である。
早速、近くの自動車教習所でライセンスを取得しようと、問い合わせてみたら、普通免許を取ってから丸二年経過していないと受験資格がないことが判明。この時、俺はフツ免を取得してから、まだ一年数ヶ月。
打つ手はない。仕方がない、監督に何とか工夫してもらおう。
一般道でカメラを回すなら、ゲリラ撮影しかないだろうと思った。

三つ目。注射である。
主人公は、覚せい剤中毒になっていく。当然、人目を忍んで,独りで自らの腕にポンプを刺し、シャブ(覚せい剤)を打つシーンがある。
中毒になると、日に何度も打ち続けているわけだから、その一連の動作は手慣れたものであることが、リアリティを生む。
この映画では、覚せい剤中毒が一つの重要なモチーフであったから、今迄の日本映画には無い新しい要素を入れたかった。
それまでの映画では、大方の注射の場面の撮影は、俳優が注射器を手にして、腕なり、身体の何処かに近づけたところで、カット。次に、注射器と手だけのアップとなる。
そして、実際に打つのは、撮影現場に控えている看護士か医者が行う。感染等の危険を想定してのことである、と思う。
クランクインするだいぶ前に、俺は監督に提案してみた。
「ねえ、監督。幸雄のシャブを打つシーンなんだけど、シャブを溶かすところから、最後にポンプ(注射器)を洗うところまで、ワンカットの長回しで撮りませんか?」
「ああ、それでいきたいねぇ。でも、根津さん、やれんの?」
「注射の練習しときますから」
ってことで、次の日から、注射の「中毒者打ち」の特訓が始まったのである。
長くなってます。もう分かってますよね?
そうです。つづきは、次回へ・・・。
では、またお会いしましょう。
昨日、遅まきながら、初ものの柿を食べました。
残念ながら、種無しでした。というのは、柿の実で一番好きなところが、種のまわりの、あのツルヌルしてる部分だからです。
あのチョット色っぽい食感が堪らないのです。

柿といえば、俺が生まれた山梨の都留の家の庭には、大きな柿の木がありました。
柿の木の他にも、松、楓等、色んな樹木が植えられていて、今思えば、かなり大規模なものでした。中央にデカイ溶岩が枯山水風に配置されていて、北側の縁に漆喰造りの二階建ての蔵。その右手に瓦屋根の裏門。そこから、隣家との堺の塀に沿って、細長い物置小屋があり、その小屋の端に、立派な柿の木はあった。木登りして遊ぶのに手頃な枝振りで、よく登ったものでした。
ところが、この木に生る実は渋柿で、生では食えない。しかし、実は沢山生るので、母が、軒下に吊るして干し柿にしたものを、おやつで食べたものでした。
軒下に整然と吊るしてある橙々色の干し柿。あの頃は、ごく当たり前の秋の懐かしい光景だったのに、今では滅多に目にする機会もない。
都会の風景は、急速に季節感を感じさせる風物を失っている。
などと、シンミリしてしまうのは、やはり「秋」が深まってきたからでしょうか?
今日は、前回の話に出た映画「さらば愛しき大地」を撮っていた時の、エピソードを紹介します。
あれは、向田邦子さんの「隣りの女」というテレビドラマに出演した、翌年であった。
マネージャーから「柳町光男監督自ら出演依頼があって、シナリオが届いてるから、読んでみて」と言われ、手渡されたのは、なんと!!!監督が自ら書いた生原稿のコピーの束であった。
出演依頼の際、普通は、きちんと製本された台本が届けられるのが当たり前だから、これには、少々驚いた。
その日の夜、ベッドに入ってから、寝る前にザッと目を通すつもりでコピーの束を読み始めた。ところが、一旦読み出したら、話の展開の早さと、濃密さと迫力に圧倒されて、一気に読み切ってしまった。その夜は興奮して中々寝つかれなかったのを覚えている。
読み終えて、「演ってみたい」と思ったと同時に、「演っていいのか」という迷いもあった。それは、俺にオファーされた主人公・幸雄の役どころに原因がある。
幼い息子二人を事故で失ったことを機に、幸雄の人生の歯車は狂い始め、愛人へ、覚せい剤中毒へと堕ちてゆき・・・というキャラクター。いわば破滅的な「汚れ役」である。
当時の俺は、二枚目路線でいっていたから、(ウォー、コッ恥ずかしい!)
この、シャブ中のダンプの運転手・幸雄役は、それ迄の根津甚八のイメージをぶち壊しかねない大きな賭けでもあったのだ。
結構迷った挙げ句、演ることにした。
やはり、シナリオの持っている力強さと、柳町監督のデビュー作「十九歳の地図」に感激していた俺は、監督・柳町光男に対する強い興味が引き金となった。
演ると決めたはいいが、「幸雄」を演じるためには、準備しなければならないことが、大きく四つあった。
一つは茨城弁をマスターすること。映画の舞台は、茨城県鹿島の田園地帯。
「幸雄」は、その一角にある農家の長男という設定である。可能な限りナチュラルである方が望ましい。それに、柳町監督自身が茨城出身であるから、なおさら完璧を目指したいと思った。
状況劇場時代に、韓国、バングラディッシュ、シリアのパレスチナキャンプ地と、それぞれの国の言語で台詞を丸暗記して上演した時、俺の台詞は、80%ぐらい通じていたという実績から、いくら馴染みのない言葉の台詞でも、集中特訓すれば茨城の人が観ても、納得させる自信はあった。
二つ目は、10トン積みダンプカーの運転。
役の職業がダンプの運転手なのだから、当然一般道での運転のシーンがある。街中を荷台を上げっ放しで、電柱をなぎ倒し暴走する場面(このシーンは、予算上等の理由で、撮影されなかった)まであるのだ。大型四輪の免許は、必須である。
早速、近くの自動車教習所でライセンスを取得しようと、問い合わせてみたら、普通免許を取ってから丸二年経過していないと受験資格がないことが判明。この時、俺はフツ免を取得してから、まだ一年数ヶ月。
打つ手はない。仕方がない、監督に何とか工夫してもらおう。
一般道でカメラを回すなら、ゲリラ撮影しかないだろうと思った。

三つ目。注射である。
主人公は、覚せい剤中毒になっていく。当然、人目を忍んで,独りで自らの腕にポンプを刺し、シャブ(覚せい剤)を打つシーンがある。
中毒になると、日に何度も打ち続けているわけだから、その一連の動作は手慣れたものであることが、リアリティを生む。
この映画では、覚せい剤中毒が一つの重要なモチーフであったから、今迄の日本映画には無い新しい要素を入れたかった。
それまでの映画では、大方の注射の場面の撮影は、俳優が注射器を手にして、腕なり、身体の何処かに近づけたところで、カット。次に、注射器と手だけのアップとなる。
そして、実際に打つのは、撮影現場に控えている看護士か医者が行う。感染等の危険を想定してのことである、と思う。
クランクインするだいぶ前に、俺は監督に提案してみた。
「ねえ、監督。幸雄のシャブを打つシーンなんだけど、シャブを溶かすところから、最後にポンプ(注射器)を洗うところまで、ワンカットの長回しで撮りませんか?」
「ああ、それでいきたいねぇ。でも、根津さん、やれんの?」
「注射の練習しときますから」
ってことで、次の日から、注射の「中毒者打ち」の特訓が始まったのである。
長くなってます。もう分かってますよね?
そうです。つづきは、次回へ・・・。
では、またお会いしましょう。