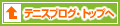注射 42006年11月20日
皆さん、いかがお過ごしですか? 根津甚八です。
もう今年も11月半ばを過ぎてしまいました。
もうしばらくしたら、街中のあちらこちらから、テレビ、ラジオ、車からクリスマスソングが溢れてくるわけで、一寸嫌な感じで胸の内がザワザワしてきます。
ついこの間、真夏のまぶしい陽光を受けながら、アツイ、アツイとぼやいていたかと思ったら、秋ももう終わりに近い。

そろそろ、朝目覚めてからベッドを抜け出す時、少しだけ気合いを入れないとならなくなってきましたね。
さて、今回も「駐車」じゃなかった、「注射」のつづきです。
注射、注射って、もうウンザリ気味でしょうが、今回で終わるはずですから・・・多分・・・。
お断りしておきます。くれぐれも息を詰つめて読まないでください。あせらず、ユッタリと流してください。
「幸雄」のシャブを打つシーンのワンカット撮りは、前日の夜、宿の一室にメインスタッフが集まり綿密な準備をした。

一見簡単そうに見えるけど、実際やると難しいのだ。
中毒者は、常に誰にも見られないように用心して打ってるわけだから、スタッフの誰もが、目の前で「中毒者打ち」など見たことがない。
それで、俺がシャブ、じゃなかったブドウ糖を水で溶かし、中毒者特有の打ち方で静注し、最後にポンプをガラスのコップに入れた水で洗浄するまでの手順と動きを、柳町監督とカメラの田村さんを中心としたスタッフ見てもらい、それを、どのアングルから、どういう風に撮影したらいいかという打ち合わせをした。
実際にフィルムを回す本番は、チャンスが1回か2回なのでミスは極力避けたい、というか、許されないからだ。
液が漏れたりしたら、途端に青あざが出たり、腫れることもあるから、は出来れば本番一発で終わらせたい。
こういう時のピーンと張りつめた緊張感のなかで、究極の集中力を発揮して演技してる自分が一番好きなんだろうと思う。
監督、カメラマンの田村正樹さん、照明のチーフ、助監督たちの前で、一連のを見せる。全員張りつめている。一段落ついたところで、見ていた助監督の一人がこんなことを言った。
「俺、自慢じゃないけど、ウィスキーを静脈注射したことあるんですよ」
一同、とたんに緊張がゆるんだ。
「だって、いちいち口から飲むのって面倒くさいじゃないっすか。」
「はあ???」
「入れると即ドッカンってきますから、酔っ払うの早いっすよ」
「・・・」
「喉乾いてる時、炭酸水も試したんすけど、あれはだめっすネ。痛くて、痛くて・・・」
バッカじゃないの、こいつ。
前日の周到な準備のおかげで、翌日の本番はスムーズにいった。
こういう日の夕食のビールは堪らなく美味いんだよね。

パンチパーマ&レイバン&ダボシャツの俺と10t.ダンプ
この「幸雄」を演る上で準備することが、もうひとつあったことを思い出した。それは、 中毒者の妄想症状である。
監督から「覚醒剤中毒」という本やら、文献資料は渡されたが、活字だけからでは、想像の域を超えられない。どうしても本物の動き、表情を、この目で見たい。
知り合いの医者を通じて、入院している中毒患者を見学したいと頼んだが、患者のプライバシーの問題で、さすがにこれは叶わなかった。
諦めかけていたら、何とタイミングのいいことに、ある日の新聞のラテ欄に、○○市の元・シャブ中の女性を追ったドキュメント番組の案内を見つけたのだ。
さすが、といっては語弊があるが、本物はやはり本物であった。その禁断症状、どんな手段を使ってでも、薬を手に入れようとする執念、喚き、号泣、怒声、虚脱感・・・。俺はむさぼるように見入っていた。
この番組の彼女の映像から、非常に強いインスピレーションを与えられた。
あの番組を作ったスタッフと、シャブ中から更生した○○市の女性に感謝
である。
ありがとうございました。
こうして、東京での準備を順調に済ませ、残った課題、10t.ダンプカーの運転の特訓と茨城弁の仕上げを兼ねて、クランクインの一週間前に、柳町監督自ら運転の監督の車で、茨城県の鹿島に入ったのである。
ヘアースタイルは、5日前に、生まれて初めてのパンチパーマにしてあった。ルームミラーに映ったそのパンチと自分の顔にそれほど違和感がないのが恐かった。
またしても、〈つづく〉と、相成ってしまいました。
また、お会いしましょう。
もう今年も11月半ばを過ぎてしまいました。
もうしばらくしたら、街中のあちらこちらから、テレビ、ラジオ、車からクリスマスソングが溢れてくるわけで、一寸嫌な感じで胸の内がザワザワしてきます。
ついこの間、真夏のまぶしい陽光を受けながら、アツイ、アツイとぼやいていたかと思ったら、秋ももう終わりに近い。

そろそろ、朝目覚めてからベッドを抜け出す時、少しだけ気合いを入れないとならなくなってきましたね。
さて、今回も「駐車」じゃなかった、「注射」のつづきです。
注射、注射って、もうウンザリ気味でしょうが、今回で終わるはずですから・・・多分・・・。
お断りしておきます。くれぐれも息を詰つめて読まないでください。あせらず、ユッタリと流してください。
「幸雄」のシャブを打つシーンのワンカット撮りは、前日の夜、宿の一室にメインスタッフが集まり綿密な準備をした。

一見簡単そうに見えるけど、実際やると難しいのだ。
中毒者は、常に誰にも見られないように用心して打ってるわけだから、スタッフの誰もが、目の前で「中毒者打ち」など見たことがない。
それで、俺がシャブ、じゃなかったブドウ糖を水で溶かし、中毒者特有の打ち方で静注し、最後にポンプをガラスのコップに入れた水で洗浄するまでの手順と動きを、柳町監督とカメラの田村さんを中心としたスタッフ見てもらい、それを、どのアングルから、どういう風に撮影したらいいかという打ち合わせをした。
実際にフィルムを回す本番は、チャンスが1回か2回なのでミスは極力避けたい、というか、許されないからだ。
液が漏れたりしたら、途端に青あざが出たり、腫れることもあるから、は出来れば本番一発で終わらせたい。
こういう時のピーンと張りつめた緊張感のなかで、究極の集中力を発揮して演技してる自分が一番好きなんだろうと思う。
監督、カメラマンの田村正樹さん、照明のチーフ、助監督たちの前で、一連のを見せる。全員張りつめている。一段落ついたところで、見ていた助監督の一人がこんなことを言った。
「俺、自慢じゃないけど、ウィスキーを静脈注射したことあるんですよ」
一同、とたんに緊張がゆるんだ。
「だって、いちいち口から飲むのって面倒くさいじゃないっすか。」
「はあ???」
「入れると即ドッカンってきますから、酔っ払うの早いっすよ」
「・・・」
「喉乾いてる時、炭酸水も試したんすけど、あれはだめっすネ。痛くて、痛くて・・・」
バッカじゃないの、こいつ。
前日の周到な準備のおかげで、翌日の本番はスムーズにいった。
こういう日の夕食のビールは堪らなく美味いんだよね。

パンチパーマ&レイバン&ダボシャツの俺と10t.ダンプ
この「幸雄」を演る上で準備することが、もうひとつあったことを思い出した。それは、 中毒者の妄想症状である。
監督から「覚醒剤中毒」という本やら、文献資料は渡されたが、活字だけからでは、想像の域を超えられない。どうしても本物の動き、表情を、この目で見たい。
知り合いの医者を通じて、入院している中毒患者を見学したいと頼んだが、患者のプライバシーの問題で、さすがにこれは叶わなかった。
諦めかけていたら、何とタイミングのいいことに、ある日の新聞のラテ欄に、○○市の元・シャブ中の女性を追ったドキュメント番組の案内を見つけたのだ。
さすが、といっては語弊があるが、本物はやはり本物であった。その禁断症状、どんな手段を使ってでも、薬を手に入れようとする執念、喚き、号泣、怒声、虚脱感・・・。俺はむさぼるように見入っていた。
この番組の彼女の映像から、非常に強いインスピレーションを与えられた。
あの番組を作ったスタッフと、シャブ中から更生した○○市の女性に感謝
である。
ありがとうございました。
こうして、東京での準備を順調に済ませ、残った課題、10t.ダンプカーの運転の特訓と茨城弁の仕上げを兼ねて、クランクインの一週間前に、柳町監督自ら運転の監督の車で、茨城県の鹿島に入ったのである。
ヘアースタイルは、5日前に、生まれて初めてのパンチパーマにしてあった。ルームミラーに映ったそのパンチと自分の顔にそれほど違和感がないのが恐かった。
またしても、〈つづく〉と、相成ってしまいました。
また、お会いしましょう。
注射 32006年11月06日
皆さん、いかがお過ごしですか? 根津甚八です。
お天道さんが顔を出してくれてると、ポッカリして気持ちが良いのですが、雲間にお隠れになってしまうと、ぞくっと寒さが走る陽気になってきましたね。
急に陽も短くなったし、冬はすぐそこまで来ています。
時々うすく戸を開けて、いつ侵入してやろうかと様子を窺っているにちがいない。
うっ、もう想像しただけでも寒いぞお!
12月生まれなのに、寒さには滅法弱いので、これからやってくる季節はあまり好きではありません。
庭の姫娑羅には、橙色から焦げ茶色に変わってしまった葉もチラホラ見えはじめました。

一年を通して四季の移り変わりがハッキリしているから、日本は色んな面で豊かなのは分かっちゃいるけど、冬だけは勘弁して欲しい。
でもこんな俺とは正反対に、暑いのが苦手で夏なんか大嫌いという人もいるんだよね。
皆さんは、どうですか? 冬派、それとも夏派?
どっちも駄目。春だけとか、秋だけとかが良いという人もいるだろうし、人それぞれですよね。
では、前回の続きのはじまりです。
テレビから流されるシャブ中男の陰惨な映像を、「いつか、何処かで使える」というような性根から、取材をしながら観ていたという話をしました。
演じるっていう行為はメッチャ面白い。
古くから、「役者と乞食は、三日やったらやめられない」と言われてるくらいですから。それだけ、一度はまったら抜けられないほど麻薬的な魅力があるということでしょう。かつて役者を河原乞食とも言いましたよね。
乞食の役はやったことがあるし、かつてバングラデッシュで乞食の群れに囲まれながら芝居を演ったこともあるけど、乞食の生活はしたことはない・・・当たり前だけれど。
でも、乞食の存り方ってわかるような気がする。
愛しい人、好きな物、誇り、拘りを断ち切れないないから、苦楽の波に揉まれながら、皆頑張って泣き笑いの人生を生きている。
しかし、家族、友人、プライド、執着等々、世俗の一切を捨てることが出来、一種の社会的蒸発者となって、持てる者からのおこぼれを恵んでもらいながら「ただ生きる」ことを決めてしまえば、それは意外に楽チンな道であることは、容易に想像がつく。
全ての社会的なしがらみから解き放たれるのだ。自分を縛りつけるものは一切ないのだから、三日やったらやめられないほど自由で気侭な日々に違いない。しかし、その代償になんの保障もない。なにかあったら、野たれ死んでいいという覚悟がいる。
役者も三日やったらやめられないほど、演じるということは魅力的であると同時に、あまりに面白いからというか、のめり込むあまりに危険な面も持ち合わせている。死にはしないけど、かなり危ない。
こうした「両刃の剣」というような要素は、何も役者だけに見られるというものではなく、どんな職業に従事しようと、ある程度長く続けているうちに、それぞれに大なり小なり職業病というものは心身に染み込んでくるものだと思うが、役者の場合、この職業病がかなり特殊で、危険な因子を内包しているということなのである。
何故か???
役者は、虚構の真っ只中へ、その肉体と感情をまるごと浸りきって、疑似体験を重ねてしまうという、芸術家のジャンルにおいても特殊だからです。
分かり易く言えば、虚と実が混じり合って混同しはじめてしまうのです。卑近な例でいえば、恋人同士を演じた二人が、つき合いはじめるなんて、よくある話じゃないですか。
能を芸術にまで高めてといわれる世阿弥の言葉に「虚実皮膜に真あり」というのがあります。
「作りごと」と「あるがまま」とがせめぎ合い、混じり合う「薄皮一枚」のところに、観る者の心に伝わる「真」があるということだと、俺は勝手に解釈してる。どちらか一方だけの、片手落ちでは人は感動しないということ。やり過ぎではなく、「ほどほど」でないといけない。
そして、より質の高いリアリティを求めはじめると、どれほど悲しい目にあって涙が流れようと、役者は、そんな自分を観察し、頭の中で冷静に演技ノートにメモしてるものなのです。実生活における恋人との関係でさえ、いつもとはかけ離れた激しい気持ちの振幅をメモしてる。
バイオリニストなら、バイオリンから離れられるけど、役者は自分の肉体と感情から一瞬たりとも離れられない。つまり、いつでもどこでも自分の表現が出来る。言い方を変えれば、いつだってどこでだって、人を騙せるということ、才能が高い役者なら、世の人々の人心を惑わし、煽動することは容易いことだともいえる。
これは危険な存在でしょう? だから、日本では、かつて河原乞食と呼ばれ身分も非人以下だったし、ヨーロッパでも、昔は役者は死んでも教会の墓地には埋葬されなかったのです。
状況劇場に入って2、3年目、一日中演技のことばかり思い続け、そんな根性がほとほと嫌になり、本気で役者をやめようと思い詰めたこともあった。
こういう役者ののめり込みぶりの悲劇を題材にした映画がある。
名匠・森 一生監督の「藤十郎の恋」(長谷川一夫主演)がある。

芸のためにお梶(京マチ子)偽りの恋を仕掛ける藤十郎
学生時代に読んだJ.Pサルトルの「キーン・天才と狂気」も、似たような題材を扱ってる。実在したシェイクスピア劇の名優をモデルにした才能溢れる俳優の悲劇である。興味ある方は、こちらもどうぞ。
役者の道に迷いを感じ始めたこの頃に読んだ、三島由紀夫のエッセイの中に、「放射能を扱う放射能科学者が、知らず知らずのうちに放射能に侵されているように、人の心を扱う芸術家も、知らないうちに、自身の心を侵される。とりわけ虚構の真っただ中に肉体と精神の両面で入り込む俳優は最も破壊され易い」というようなことを書いていたが、見事に見抜いている。
その三島由紀夫は、虚実混交した彼自身の美学の中に自らの死さえも組み込んでしまった。川端康成が予言した通り、己の才能に殺されたとも言える。
俺には、藤十郎もキーンも、三島由起夫にダブって見えてしかたない。
あれ、何の話だっけ? えらく脱線してしまったぞ。
そう、シャブ中男のことだった。
「さらば・・・」の中で、蟹江敬三さん演ずるダンプ仲間に、シャブを打ってやるシーンがあった。
蟹江さんは、まさか相手役の俺にマジで注射されるとは、予想外の仰天の出来事であったにちがいない。
「ホントにだいじょうぶなの?」
「大丈夫だって。特訓したから、うまいもんだよ。例え空気が入っても、チョット痛いだけ。死なないんだってさ」
「緊張するなぁ」
「それに、これブドウ糖だから。元気になるよ。じゃ、ちょとチクッとするよ」
この時の蟹江さんのビビリ方は、半分以上マジであったと思う。しかし、このシーンにはどんピシャでした。
今考えれば、かなりの無茶やってましたね。
気がついたら、もうこんなに書いてる。
では、またまた次回につづくということで・・・。
また、お会いしましょう。
お天道さんが顔を出してくれてると、ポッカリして気持ちが良いのですが、雲間にお隠れになってしまうと、ぞくっと寒さが走る陽気になってきましたね。
急に陽も短くなったし、冬はすぐそこまで来ています。
時々うすく戸を開けて、いつ侵入してやろうかと様子を窺っているにちがいない。
うっ、もう想像しただけでも寒いぞお!
12月生まれなのに、寒さには滅法弱いので、これからやってくる季節はあまり好きではありません。
庭の姫娑羅には、橙色から焦げ茶色に変わってしまった葉もチラホラ見えはじめました。

一年を通して四季の移り変わりがハッキリしているから、日本は色んな面で豊かなのは分かっちゃいるけど、冬だけは勘弁して欲しい。
でもこんな俺とは正反対に、暑いのが苦手で夏なんか大嫌いという人もいるんだよね。
皆さんは、どうですか? 冬派、それとも夏派?
どっちも駄目。春だけとか、秋だけとかが良いという人もいるだろうし、人それぞれですよね。
では、前回の続きのはじまりです。
テレビから流されるシャブ中男の陰惨な映像を、「いつか、何処かで使える」というような性根から、取材をしながら観ていたという話をしました。
演じるっていう行為はメッチャ面白い。
古くから、「役者と乞食は、三日やったらやめられない」と言われてるくらいですから。それだけ、一度はまったら抜けられないほど麻薬的な魅力があるということでしょう。かつて役者を河原乞食とも言いましたよね。
乞食の役はやったことがあるし、かつてバングラデッシュで乞食の群れに囲まれながら芝居を演ったこともあるけど、乞食の生活はしたことはない・・・当たり前だけれど。
でも、乞食の存り方ってわかるような気がする。
愛しい人、好きな物、誇り、拘りを断ち切れないないから、苦楽の波に揉まれながら、皆頑張って泣き笑いの人生を生きている。
しかし、家族、友人、プライド、執着等々、世俗の一切を捨てることが出来、一種の社会的蒸発者となって、持てる者からのおこぼれを恵んでもらいながら「ただ生きる」ことを決めてしまえば、それは意外に楽チンな道であることは、容易に想像がつく。
全ての社会的なしがらみから解き放たれるのだ。自分を縛りつけるものは一切ないのだから、三日やったらやめられないほど自由で気侭な日々に違いない。しかし、その代償になんの保障もない。なにかあったら、野たれ死んでいいという覚悟がいる。
役者も三日やったらやめられないほど、演じるということは魅力的であると同時に、あまりに面白いからというか、のめり込むあまりに危険な面も持ち合わせている。死にはしないけど、かなり危ない。
こうした「両刃の剣」というような要素は、何も役者だけに見られるというものではなく、どんな職業に従事しようと、ある程度長く続けているうちに、それぞれに大なり小なり職業病というものは心身に染み込んでくるものだと思うが、役者の場合、この職業病がかなり特殊で、危険な因子を内包しているということなのである。
何故か???
役者は、虚構の真っ只中へ、その肉体と感情をまるごと浸りきって、疑似体験を重ねてしまうという、芸術家のジャンルにおいても特殊だからです。
分かり易く言えば、虚と実が混じり合って混同しはじめてしまうのです。卑近な例でいえば、恋人同士を演じた二人が、つき合いはじめるなんて、よくある話じゃないですか。
能を芸術にまで高めてといわれる世阿弥の言葉に「虚実皮膜に真あり」というのがあります。
「作りごと」と「あるがまま」とがせめぎ合い、混じり合う「薄皮一枚」のところに、観る者の心に伝わる「真」があるということだと、俺は勝手に解釈してる。どちらか一方だけの、片手落ちでは人は感動しないということ。やり過ぎではなく、「ほどほど」でないといけない。
そして、より質の高いリアリティを求めはじめると、どれほど悲しい目にあって涙が流れようと、役者は、そんな自分を観察し、頭の中で冷静に演技ノートにメモしてるものなのです。実生活における恋人との関係でさえ、いつもとはかけ離れた激しい気持ちの振幅をメモしてる。
バイオリニストなら、バイオリンから離れられるけど、役者は自分の肉体と感情から一瞬たりとも離れられない。つまり、いつでもどこでも自分の表現が出来る。言い方を変えれば、いつだってどこでだって、人を騙せるということ、才能が高い役者なら、世の人々の人心を惑わし、煽動することは容易いことだともいえる。
これは危険な存在でしょう? だから、日本では、かつて河原乞食と呼ばれ身分も非人以下だったし、ヨーロッパでも、昔は役者は死んでも教会の墓地には埋葬されなかったのです。
状況劇場に入って2、3年目、一日中演技のことばかり思い続け、そんな根性がほとほと嫌になり、本気で役者をやめようと思い詰めたこともあった。
こういう役者ののめり込みぶりの悲劇を題材にした映画がある。
名匠・森 一生監督の「藤十郎の恋」(長谷川一夫主演)がある。

芸のためにお梶(京マチ子)偽りの恋を仕掛ける藤十郎
学生時代に読んだJ.Pサルトルの「キーン・天才と狂気」も、似たような題材を扱ってる。実在したシェイクスピア劇の名優をモデルにした才能溢れる俳優の悲劇である。興味ある方は、こちらもどうぞ。
役者の道に迷いを感じ始めたこの頃に読んだ、三島由紀夫のエッセイの中に、「放射能を扱う放射能科学者が、知らず知らずのうちに放射能に侵されているように、人の心を扱う芸術家も、知らないうちに、自身の心を侵される。とりわけ虚構の真っただ中に肉体と精神の両面で入り込む俳優は最も破壊され易い」というようなことを書いていたが、見事に見抜いている。
その三島由紀夫は、虚実混交した彼自身の美学の中に自らの死さえも組み込んでしまった。川端康成が予言した通り、己の才能に殺されたとも言える。
俺には、藤十郎もキーンも、三島由起夫にダブって見えてしかたない。
あれ、何の話だっけ? えらく脱線してしまったぞ。
そう、シャブ中男のことだった。
「さらば・・・」の中で、蟹江敬三さん演ずるダンプ仲間に、シャブを打ってやるシーンがあった。
蟹江さんは、まさか相手役の俺にマジで注射されるとは、予想外の仰天の出来事であったにちがいない。
「ホントにだいじょうぶなの?」
「大丈夫だって。特訓したから、うまいもんだよ。例え空気が入っても、チョット痛いだけ。死なないんだってさ」
「緊張するなぁ」
「それに、これブドウ糖だから。元気になるよ。じゃ、ちょとチクッとするよ」
この時の蟹江さんのビビリ方は、半分以上マジであったと思う。しかし、このシーンにはどんピシャでした。
今考えれば、かなりの無茶やってましたね。
気がついたら、もうこんなに書いてる。
では、またまた次回につづくということで・・・。
また、お会いしましょう。