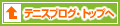3「紅テントが無い」2006年06月19日
梅雨の季節が一番苦手な、甚八です。この鬱陶しい日々、みなさん、元気にやってますか?
ところで日本VSクロアチア戦。川口はオーストラリア戦と同じくまさに守護神だった。あのPKクリアーで、日本のリズムになって、この調子で押していけば、ひょっとしたら勝てるかもと期待したけど、やはり最後のあと一歩というところでどうしてもゴールを奪えないといういつものパターン。日本にはエースストライカーがいないから仕方ないのかな。でも、オーストラリア戦に続いて、昨日もまた本当に悔しい一夜でした。
では、前回の続編です。
「唐十朗のスピリットは、俺のこの肉体にすでに染みこんでいる!」
これだけ熱い思いを胸に抱いているのだ、状況劇場に入りたい動機としては充分である。だから、芝居を観たことがないことをフツーに伝えた。
しかし一般常識からすれば、実際の舞台も観ていないで劇団に入りたいなどという人間は、はなから無視されて当然。普通ならこの時点で一巻の終わりだったろう。入団の望みはここで断たれていたかもしれない。
しかし、何故かチャンスは繋がった。「うちの芝居を観てから、また電話しなさい」
二十歳そこそこの非常識な若造に、何故こんなにも丁寧に対応してくれたのか?という一つの謎、そして入団試験当日のさらなる奇妙な対応の謎も、ここではまだ他に置いといていただいてと…。
ってなわけで、教えられた公演当日、俺は勇んでタイソウジ(太宗寺)へ出かけていった。ところが、寺の境内のどこにも紅テントらしき物など見当たらないではないか。 すると、奥の方で大声をあげている人がいる。
「今日の、公演は、場所が変わりました、明大の和泉校舎です」近づいてゆくと、「急にお葬式が入ちゃってお寺では出来なくなりましたので、こちらでやります」と案内図を渡された。大急ぎで明大和泉のキャンパスにたどり着くと、そこに紅テントはあった。懐かしいようで、どこか恐ろし気な異様な雰囲気で立っていた。中に入ると、何故か子供のころに覗いた見せ物小屋を思い出した。やがて、フルートのおどろおどろしいメロディとともに「腰巻きお仙」は始まった。本からイメージした思い入れが強すぎたせいか、割と冷静に観ていたことを覚えている。芝居が終わるころには、心中密かに「役者として自分の入り込む隙間はある」というまったく根拠のない自信のようなものを抱いていた。
「昨日、芝居を観ました」
「…そう…」
「気持ちはかわりません。それで、試験日はいつでしょうか?」
「待って下さい。……それじゃね、○月○日の○時に、こちらに来てください。」劇団の稽古場の住所、道順を聞いて電話を切った。
こうして、ひとまず入団試験を受けられるところまではこぎ着けたのであった。
しかし、試験当日、俺はまたしてもとんでもないヘマをやらかしてしまう。ところが事態はまたしても予想外の展開となり、いよいよ憧れの鬼才・唐十朗と対面することとなるのである。
つづきはまたの機会をお楽しみ。思いもよらぬ展開はまだまだ続くのです。今回はここまでとさせてもらいましょう。
では、またお会いしましょう。
ところで日本VSクロアチア戦。川口はオーストラリア戦と同じくまさに守護神だった。あのPKクリアーで、日本のリズムになって、この調子で押していけば、ひょっとしたら勝てるかもと期待したけど、やはり最後のあと一歩というところでどうしてもゴールを奪えないといういつものパターン。日本にはエースストライカーがいないから仕方ないのかな。でも、オーストラリア戦に続いて、昨日もまた本当に悔しい一夜でした。
では、前回の続編です。
「唐十朗のスピリットは、俺のこの肉体にすでに染みこんでいる!」
これだけ熱い思いを胸に抱いているのだ、状況劇場に入りたい動機としては充分である。だから、芝居を観たことがないことをフツーに伝えた。
しかし一般常識からすれば、実際の舞台も観ていないで劇団に入りたいなどという人間は、はなから無視されて当然。普通ならこの時点で一巻の終わりだったろう。入団の望みはここで断たれていたかもしれない。
しかし、何故かチャンスは繋がった。「うちの芝居を観てから、また電話しなさい」
二十歳そこそこの非常識な若造に、何故こんなにも丁寧に対応してくれたのか?という一つの謎、そして入団試験当日のさらなる奇妙な対応の謎も、ここではまだ他に置いといていただいてと…。
ってなわけで、教えられた公演当日、俺は勇んでタイソウジ(太宗寺)へ出かけていった。ところが、寺の境内のどこにも紅テントらしき物など見当たらないではないか。 すると、奥の方で大声をあげている人がいる。

「今日の、公演は、場所が変わりました、明大の和泉校舎です」近づいてゆくと、「急にお葬式が入ちゃってお寺では出来なくなりましたので、こちらでやります」と案内図を渡された。大急ぎで明大和泉のキャンパスにたどり着くと、そこに紅テントはあった。懐かしいようで、どこか恐ろし気な異様な雰囲気で立っていた。中に入ると、何故か子供のころに覗いた見せ物小屋を思い出した。やがて、フルートのおどろおどろしいメロディとともに「腰巻きお仙」は始まった。本からイメージした思い入れが強すぎたせいか、割と冷静に観ていたことを覚えている。芝居が終わるころには、心中密かに「役者として自分の入り込む隙間はある」というまったく根拠のない自信のようなものを抱いていた。
「昨日、芝居を観ました」
「…そう…」
「気持ちはかわりません。それで、試験日はいつでしょうか?」
「待って下さい。……それじゃね、○月○日の○時に、こちらに来てください。」劇団の稽古場の住所、道順を聞いて電話を切った。
こうして、ひとまず入団試験を受けられるところまではこぎ着けたのであった。
しかし、試験当日、俺はまたしてもとんでもないヘマをやらかしてしまう。ところが事態はまたしても予想外の展開となり、いよいよ憧れの鬼才・唐十朗と対面することとなるのである。
つづきはまたの機会をお楽しみ。思いもよらぬ展開はまだまだ続くのです。今回はここまでとさせてもらいましょう。
では、またお会いしましょう。